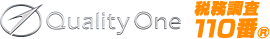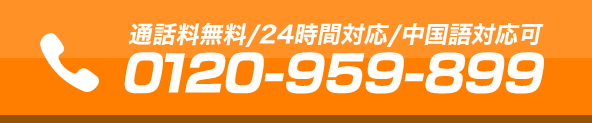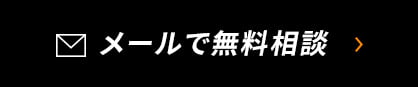目次
はじめに
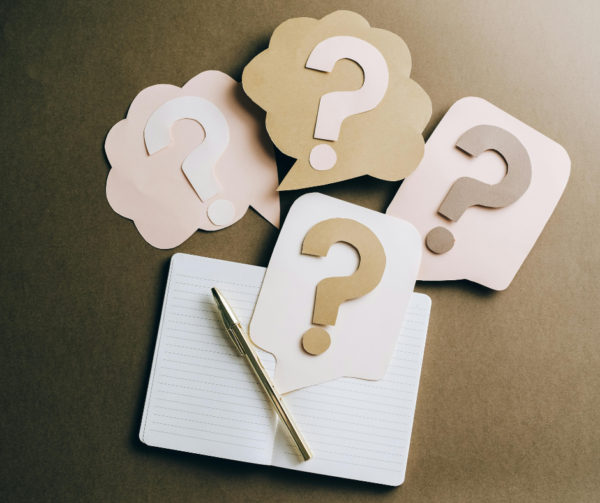
「税務調査って、いつ来るの?」
そんな疑問をお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか。
実は税務調査には、入りやすい“季節的傾向”があります。
この記事では、税務調査の入りやすい時期とその理由、調査対象となりやすい企業の特徴や対策方法について、分かりやすく解説します。
調査に備えたい経営者の皆様、ぜひ最後までご覧ください。
現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」
という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

第1章:税務調査のピークは「秋」

調査が多くなる時期
税務調査は、毎年9月~11月がピークとされています。
法的に決まっているわけではありませんが、税務署の年間スケジュールから見てもこの時期が最も動きやすいタイミングです。
第2章:税務署の年間業務スケジュールとは?

2月〜3月:確定申告で繁忙
個人事業主の確定申告(2/16〜3/15)対応で、税務署は大忙し。この時期の調査はほぼありません。
5月〜6月:企業の決算対応
3月決算の法人が多いため、税務署も決算業務で手いっぱい。この時期も調査の確率は極めて低いです。
7月:人事異動で調査なし
税務署は6月で年度末。7月は人事異動が行われ、新体制への移行でバタバタしています。
8月〜11月:調査の本格始動
お盆明けの8月末ごろから徐々に調査が開始され、9月〜11月が最も調査件数の多い時期になります。
第3章:税務調査はそもそもどのくらいの確率で来るの?

税務調査の実施件数は思っているより少なく、次のようなデータがあります。
法人:3.2%
個人:1.1%
つまり、法人の96.8%、個人の98.9%は調査を受けていないということです。
また、調査の頻度には傾向があります。
指摘が多かった場合 → 約3年に1回
指摘が少なかった場合 → 5~10年空くことも
第4章:調査対象になりやすい企業の特徴とは?

税務署はどうやって対象を選んでいる?
税務署では、企業の申告状況や経営状況を分析し、「怪しい」と思われる企業に優先的に調査を入れています。
調査対象になりやすい企業の条件
〇黒字が続いている企業:徴収の可能性が高いため
〇急成長中の企業:売上急増による申告漏れリスク
〇経費の異常増加:退職金・貸倒損失などが不自然な場合
〇経営陣の交代や事業再編があった企業
第5章:実際に調査で見られるポイント

税務調査では以下のような点が重点的にチェックされます。
〇売上の計上タイミングや漏れ
〇経費処理(特に交際費、在庫、人件費)
〇架空人件費の有無
〇領収書・請求書などの保存状況
調査担当官は「不自然な点」を重点的に確認します。
そのため、日頃の証憑管理や経理処理が問われることになります。
第6章:税務調査に備えて今からできること
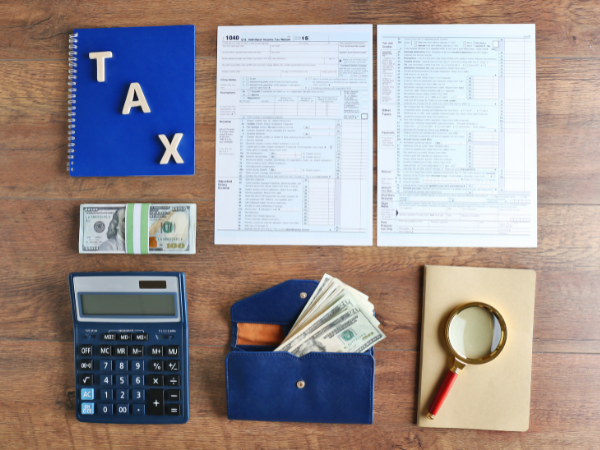
正しい知識と証拠の管理がカギ
〇領収書には取引先名・日付をメモ
〇書類の紛失を防ぎ、整理して保管
〇社内だけでなく税理士との連携を強化
正しい経理処理と証拠の保管ができていれば、調査を恐れる必要はありません。
おわりに

税務調査は避けられないリスクの一つですが、その傾向や準備方法を知っておくだけで不安は大きく軽減されます。
毎年秋は調査が集中しやすい時期。だからこそ、それ以前に「経理体制の見直し」や「証拠資料の整理」を行っておくのがベストです。
大切なのは、正しく・透明な処理を日頃から積み重ねること。
信頼できる税理士とともに、どんな調査にも対応できる体制を築いていきましょう。
こちらの動画でも詳しく説明しておりますので併せてご視聴ください。