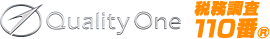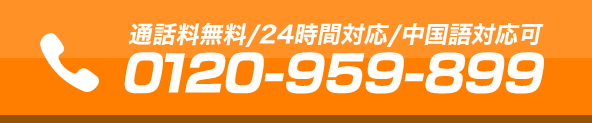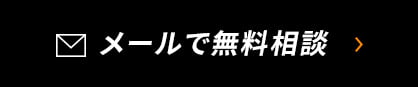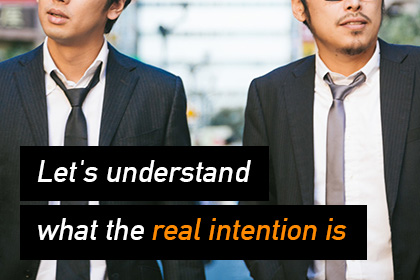目次
はじめに

これまでの2回にわたって、税務調査の全体像や基本的な流れについて説明してきました。
第1回目・第2回目の記事はこちらです。
いざ調査対象となったとき、どのような心構えで臨めばよいのか。具体的にどう対応すれば損をせずに済むのか。
それを理解しておくことは、調査を受ける側にとって大きな安心感と防御力につながります。
今回のテーマは、税務調査の「入り口」となる税務署からの最初の連絡にどう対応するか。
この段階での一挙手一投足が、後々の調査の展開を大きく左右します。
この記事では、税務署側の事情も踏まえて、やるべきこと・やってはいけないことを徹底的に解説していきます。

税務署からの連絡、その目的は?
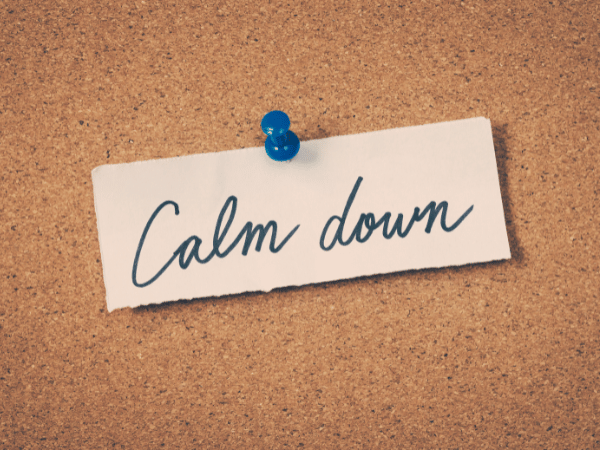
税務署が納税者に連絡を入れるのには、主に次の3つの目的があります。
- 法的手続きとしての事前通知
- 加算税の課税のために「調査通知をした」という事実を記録するため
- 調査日程の調整・確定のため
このうち特に重要なのが「事前通知」。
税務調査は、調査対象者に通知をしてから一定の期間をおいて実施されるのが原則です。
この通知をもって「調査に着手した」と記録され、税務署内では進捗管理の起点となります。
つまり、連絡を入れるという行為自体が、担当官にとって一つの任務の達成なのです。
担当官は、その後の調査スケジュールの進行、報告、上司からのプレッシャーといった複数の要素を背負いながら業務を進めています。
この裏事情を知っておくだけでも、「税務署から電話が来た=何か悪いことをしたに違いない」
といった必要以上の不安を和らげることができるはずです。
連絡を受けたときに、やるべきこと

税務署からの連絡を受けたときにまずやるべきことは、以下の通りです。
1. とにかく落ち着くこと
最初の電話対応、あるいは訪問対応では、第一印象が非常に重要です。
慌てた様子を見せると、「何か隠しているのでは?」と誤解を与える可能性があります。
おすすめの対応方法
- 電話なら「少々お待ちください」と言って保留にして、10〜30秒程度深呼吸
- 来訪なら一度席を外し、視界から外れて落ち着く時間を確保
※ただし、1分以上待たせるのは逆効果。あくまで“冷静に見える”程度の対応を。
2. 担当官の情報を聞き取る
以下の情報を必ずメモしてください。
- 税務署名(自分の住所地・本店所在地を所管しているか)
- 所属部署(一般調査か、専門官による特別調査か)
- 氏名(役職や過去の実績が分かる場合も)
- 連絡先(電話番号、内線番号)
所属部署が「特別国税調査官」「○○専門官」などであれば、不正の端緒があると見られている可能性が高いです。
こうした専門部署は、経験豊富なエース級の職員が配置されており、調査も厳しい傾向があります。
3. 調査内容の通知項目を確認する
- 調査の対象者(法人か個人か、誰の申告についてか)
- 対象税目(法人税・消費税・所得税など)
- 調査期間(通常は3年~5年)
- 臨場希望日(早ければ早いほど、要注意)
- 来訪する人数(人数で相手の目的や経験値を推測)
たとえば、複数名での訪問予定であれば、調査が大規模である可能性や、担当官の教育目的で指導役が同行していることもあります。
絶対にやってはいけない対応

1. 慌てること
→ 不信感を与えるだけで、調査が厳しくなる原因になります。
2. すぐに臨場日を設定すること
→ 不正を疑われている場合、証拠保全のために急がれている可能性があります。
→ 原則、1か月程度後に設定して、準備期間を確保しましょう。
3. 具体的な取引先名などを話すこと
→ 担当官に「事実を知っていた」と認定され、「更正等の予知」に該当するリスクがあります。
4. 調査理由を聞くこと
→ 調査目的を探る行為自体が“自覚”の裏返しと捉えられる可能性があります。
「更正等の予知」と重加算税の関係
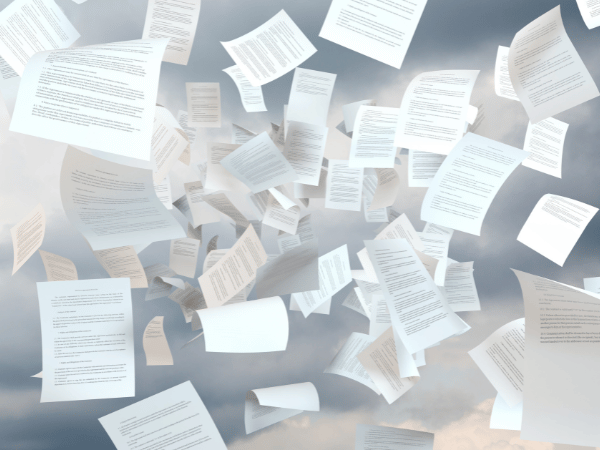
調査開始後の修正申告のタイミングによって、加算税の額や重加算税の適用リスクが変わります。
特に注意したいのが、「更正等の予知」があったかどうか。
税務署がすでに違反事実を把握していたとみなされた場合、自主的な修正申告とはみなされず、重加算税が課される可能性が高くなります。
したがって、無用な発言・質問をしないことが、自分の身を守ることにつながるのです。
まとめ:連絡対応で差がつく税務調査の成否

税務署からの連絡は、ある日突然やってきます。
しかし、その最初の対応こそが、その後の調査の展開を左右する重要なターニングポイントです。
- 焦らず、冷静に対応する
- 担当者情報・調査情報を的確に記録する
- 不必要な発言は避ける
- 臨場日までに最低1か月の準備期間を確保する
税務署とのやり取りは、「事実」と「対応力」の勝負です。
どんなときでも慌てずに、正しい順序と準備で対応することが最大の防御策となります。
もっと詳しく知りたい方は↓の動画もおすすめです。ぜひこちらもご視聴ください。