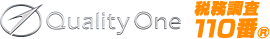今回の記事では、税務調査後、課税処分等の取消訴訟を提起する際の国の組織的対応や訴訟代理人について解説していきます。
目次
訴訟提起に対する国の組織的対応

東京法務局等の大きな地方法務局には訟務部が設置され、国を相手とした訴訟に対応しています。訟務部に所属する部付検事は、国に利害のあるあらゆる行政事件や民事事件(例えば、優生保護法関係、基地問題、医療過誤、難民申請、税金、その他)を担当しており、様々な行政庁等の訴訟における法廷活動を言わば弁護士として行っています。
これを補佐するために、訴訟となった処分等の詳細を知る各行政庁等の職員が指定代理人(訴訟代理人と同じように訴訟行為を行うことができ、弁護士と同じ立場になります。)となり、事件の主張書面の原案を作成したり証拠の準備をしたり、部付検事とともに出廷するなどして訴訟活動の一旦を担っています。
国税に関しては、処分数も多く、その結果訴訟件数が多いため、それに対応するために各国税局内には訟務官室という訴訟対応を専門とする部署が置かれています。他の行政庁でこのような専門部署を設けているのは珍しく、大量に処分が行われている国税ならではの組織で、その専門職としての能力については、法務局からも高い評価を受けています。
このように、税務訴訟に対しては、法務局の部付検事と国税局職員がチームを組んで対応しており、審判所における国税局の対応(国税局の審理担当の職員が審判所へ提出する書面を作成。)とは段違いのレベルのメンバーを揃えています。
国税側は、審判所で処分が取消しとなってしまうのは致し方ないとしても、審判所で取り消されずに勝ったものを、訴訟で負けることは絶対に許されないと思っています。
したがって、国税の裁判は、地裁や高裁で敗訴しても、ほぼ確実に最高裁まで争ってきます。
税務訴訟には和解はなく、勝つか負けるかのハードな訴訟となるので、訴訟提起を考えるならば、税務訴訟の経験が豊富な弁護士事務所に相談することが重要です。
国税局の訴訟担当

東京国税局の課税第一部の訟務官室(徴収部にも徴収関係訴訟を担当する訟務官室があります。)には、総務担当(庶務係)数名も含め70人ほど配属されており、大所帯となっています。
東京局の訟務官室は、所得班、法人班、資産班、国際班及び査察班に分かれて事件を担当しており、事件が発生すると、訟務官、主査(あるいは総括主査か訟務専門官)と実査官の計3名が指定代理人としてその事件を担当します。
これに、法務局の部付検事1名と訟務官室から法務局に出向している者1名が指定代理人となって、部付検事の指示のもとに、最低5名以上のチームで訴訟対応をしていくのが一般的です。
ですので、法廷では、被告席(税務署側)に5人以上が座っているのですが、原告席(納税者側)は弁護士が一人というような状況もよくあります。
このように、国側は、税務訴訟専門の組織的集団によって訴訟対応を行っているので、訴訟を提起するならば、租税訴訟の経験が豊富な弁護士事務所へ相談することが重要です。
また、問題となった取引、帳簿及び適用条文などについては、顧問税理士や調査時に関与した税理士がよく理解しているはずですので、これらの者も交えて、訴訟の提起をすべきか否かを早急に検討し、結論を出す必要があります。
誰を訴えてどこへ提起するのか

行政訴訟事件の被告と裁判所
行政処分の取消しを求める行政事件訴訟は、簡易裁判所では扱わないので(裁判所法33①一)、訴状の提出先は地方裁判所になります。
税務署長が行った課税処分の取消訴訟であれば、被告を国として提訴します。処分の取消訴訟は、「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」と定められています(行訴法12①)。
被告である国の住所は、法務省の所在地(千代田区霞が関1-1-1)とされていますので、東京地方裁判所に訴状を提出するか、処分をした行政庁(税務署等)の所在地を管轄する地裁に提訴することとなります。そのほか、原告(納税者)の住所を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができます(行訴法12④)。
行政事件の法廷
行政事件は、平成元年の全国の地裁への提起数は833件でしたが、その後徐々に上昇し、平成24年には2,476件にも達しています。その後は少し減少し、令和2年には1692件にまで減少しましたが、またやや上昇し、令和4年には1,834件となっています(裁判所データブック2023)。
現在、東京地方裁判所は行政事件について専門部を設けており、民事第2部,第3部,第38部及び第51部(平成26年設置)が行政専門部で、同地裁に提訴した場合は、これらのうちのいずれかの部に係属することになります。なお、これらの各行政専門部においては、3人の裁判官の合議体により裁判は行われています。
訴訟代理人となれるのは弁護士

訴訟には弁護士が必須ではありませんが、法廷では、準備書面、甲号証、乙号証、抗弁、認否、陳述、証拠調べ等々、聞き慣れない専門用語が使われますし、法廷での裁判官とのやり取りで、うっかり自分に不利な発言をしてしまう恐れもあり、通常は、訴訟代理人を定めて訴訟行為を代理してもらいます。
訴訟上の一切の行為を行うことができる訴訟代理人には、地方裁判所以上は弁護士でなければなりません(民訴法54①)。税理士は訴訟代理人とはなれません
税理士の補佐人制度

裁判には、当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができるとされています(民訴法60①)。この場合の補佐人には、公的な資格は必要ありません。
税理士は、上記2の訴訟代理人の資格はありませんが、平成13年の税理士法の改正により、租税に関する事項について、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができこととされました(税理士法2の2)。これ以前は、民事訴訟法60条1項の定めによる補佐人として出頭の許可を裁判所に求めても、担当の弁護士が税理士の資格も持つので不要だとして却下されることが多かったようです。
法改正後は、出頭についての裁判所の許可は不要ですが、弁護士名で税理士の⚪︎⚪︎人に選任したという補佐人選任届を提出します。
これにより、毎年の申告や調査時等から関わってきた顧問税理士、あるいは税務訴訟の専門知識をもつ税理士も訴訟時から参加して、納税者を援護することができることとなりました。もちろん、顧問税理士等が必ず補佐人にならなければならないというものではありません。
補佐人税理士は、訴訟代理人である弁護士とともに口頭弁論期日に出頭し陳述することができますが、弁護士が出廷しない場合には、陳述はできません。
陳述については、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされます。ただし、訴訟代理人はその陳述について、直ちに取り消すことができるとされています(税理士法2の2②)。
税務訴訟は、税についての高度な専門知識を要するので、補佐人税理士の制度は、弁護士にとっても有益な手段となっていると考えらえます。