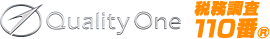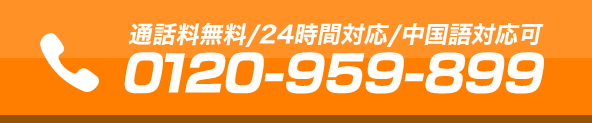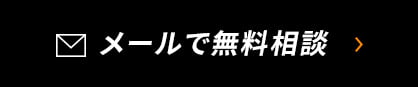目次
はじめに

脱税や無申告、海外資産の申告漏れに対する調査は年々厳しくなっており、特に近年では国際的な情報交換制度の発展により、海外に資産を持つ納税者への監視体制も強化されています。
この記事では、国税当局が毎年発表している「査察の概要」をもとに、査察調査の最新の傾向と、国際事案や海外資産の申告に対する対応の基本について解説します。
税務対応の現場に関わる方はもちろん、経営者や個人投資家の方々にとっても、重要な知識となる内容です。ぜひ参考にしてください。
現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」
という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

1 査察調査の概要

例年6月に前年度の査察の調査実績の概要が発表されます。
その発表資料の「令和6年度 査察の概要」について簡単に紹介します。
査察調査には151件着手し、98件(65.3%)を告発。ほぼ前年並みの件数です。
脱税額は、総額112億7千万円(7千5百万円/件)、告発分は82億3千万円(8千4百万円/件)で、去年に続き、若干、金額は減少しています。
税目別の告発件数は、法人税48件、消費税29件(内不正還付17件)、所得税16件、源泉所得税3件、相続税2件で、4、5年前に比べると消費税事件が10件前後増加しています。
告発の多かった業種は、ここ数年常に上位4種に入っている、建設業21件、不動産業11件、人材派遣業5件でした。
2 査察事件で重点的に取り組んだとされる内容

重点的に取り組んだとして挙げられているのは、消費税事案、無申告事案、及び国際事案です。
最初に挙げられているのは消費税事案で、仕入税額控除や輸出免税制度の悪用、課税売上割合の偽装などによる不正還付事案について、国庫金の搾取ともいえ悪質性が高い事件として紹介しています。
無申告事案は、動画配信やネット取引関連の無申告や、自社株の譲渡所得の無申告など13件を告発したとし、そのうち、不正はないとしても故意に申告書を提出しない逋脱事件は8件であったと紹介しています。
これは、仮装や隠蔽行為がなく、単純に無申告であっただけでも、無申告逋脱犯として告発されているということです。
昨年も、忙しいという理由だけで数年間申告を放置していた漫画家を告発し、ニュースになりましたが、単なる無申告でも、税額が数年分を合わせて数千万円にもなると、査察によって告発されて刑事事件の被告人となることがあるということです。
国際事案については20件を告発したとし、除外した資金を海外口座や暗号資産の海外取引所に預けていたことなどが紹介されています。
国際事案の調査については、租税条約に基づく外国税務当局等と情報交換制度を活用したとしています。
3 海外資産と国外財産調書

海外関連事案の調査については、査察だけが行っているのではありません。
インターネット上での取引が当たり前となり、ネットを通じて海外との取引が容易にできるようになっていることから、海外取引については、各税務署においても重点調査の対象とされています。また、いくつかの署には海外取引調査の部門が設置されています。
なお、令和5年12月末時点の国外財産総額は、提出された国外財産調書(提出件数13,242件)の記載額において、6兆4,897億円(前年対比+13.4%)にも上っています。
課税当局も、以前とは違い、海外資産や海外取引の情報を容易に手に入れることができるようになっていますので、国外財産を安易に国外財産調書から除外し、その資産から生じる所得を除外すると、加算税の加重措置(+5%)の適用を受けることになります。
また、調査において国外財産に係る資料を提示しない場合は、さらに加算税が5%加重されることになります。
4 租税条約等に基づく情報交換の概要

国際的な脱税及び租税回避に対処するため、租税条約等の規定に基づき、各国が連携して情報交換を行っています。
その仕組みを大きく分けると、①自動的情報交換、②自発的情報交換、③要請に基づく情報交換があり、自国の非居住者についての情報を、定期的に各国間で交換しています。
上記①の自動的情報交換により受領・提供した情報数が一番多く、その内容は以下のものになります。
①CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)に基づく非居住者の金融口座情報(氏名、住所、口座残高等)の交換。
②国別報告書(CbCR(Country by Country Report):多国籍企業グループの国ごとの活動状況に関する国別報告書)の交換。
③法定調書情報(利子、配当、不動産賃借料、無形資産の使用料、給与・報酬、株式の譲受対価等の情報)の交換。
令和5事務年度にCRSにより提供された金融口座数は約246万件(対前年比97.2%)、法定調書情報は約130万件(対前年比169.2%)と発表されており(令和7年1月付「令和5事務年度租税条約等に基づく情報交換事績の概要」)、活発な情報交換が行われています。
また、要請に基づく情報交換として、相手国に特定の情報について調査依頼を行っても、以前に比べてスムーズに素早く回答が返って来るようになってきています。
なお、暗号資産についても、令和9年から情報交換が開始されます。
調査において海外資産の状況を尋ねられた場合、調査官は上記の情報を得ている可能性がありますので、回答に当たっては漏れの無いように回答する必要があります。
また、何らかの海外資産に係る申告漏れがあったような場合には、早急に修正申告を行うこととするのが最善策だと思います。
おわりに
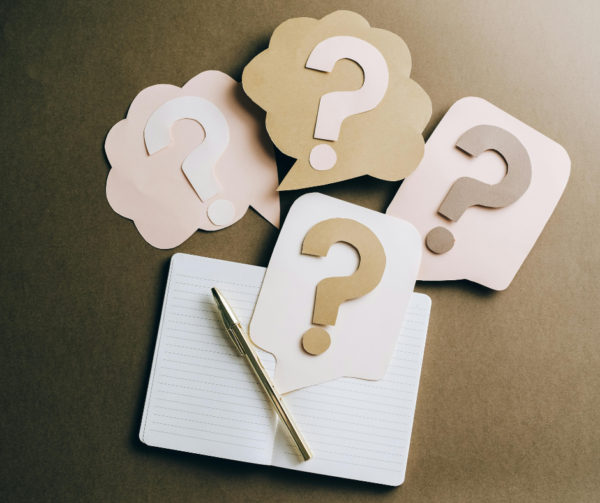
今回ご紹介したように、税務当局は年々高度なAI情報ネットワークを駆使し、無申告・不正還付・国際的な資産移転に対する監視体制を強化しています。
特に海外資産や仮想通貨に関する情報は、国際的な情報交換制度を通じて共有されるため、「海外だからバレない」といった感覚はもはや通用しません。
誤って申告漏れがあった場合でも、意図的でなければ早期の修正申告で大きなリスクを回避できる可能性があります。
調査の対象にならないためには、日頃から適正な申告と資料の整備、海外資産の把握が不可欠です。
今後もこのような最新動向を押さえ、正しい対応を心がけましょう。
また以下の記事、およびYou tube動画も併せてご覧ください。