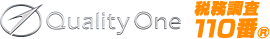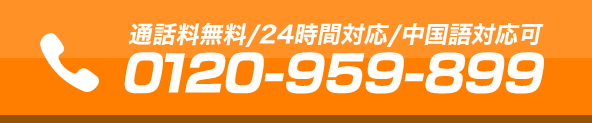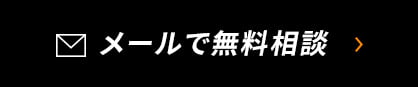目次
はじめに
「税務調査で最悪の場合、逮捕されることはあるのか?」
税務署から連絡が来ただけで不安になる方も多いはずです。
この記事では、年間130件以上の税務調査対応を踏まえ、逮捕の可能性があるケース、通常調査と査察(強制調査)の違い、そして無予告来訪時の対応ポイントまで、わかりやすく整理してお伝えします。
今回は、最高裁で大きな判断が下された平成29年12月15日の判決を中心に、その経緯と注意点をわかりやすく解説します。
動画でも詳しく解説しております。
現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」
という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

第1章 基本は逮捕されない?

冒頭の結論はシンプルです。逮捕される可能性はある。
けれども、基本は逮捕されません。
通常の税務調査は行政調査であり、最終的には修正申告と納税で終わるのが一般的です。
「税務署から連絡が来た=即逮捕」という図式ではありません。
では、どんなときに逮捕の可能性が生まれるのか。
カギは査察(強制調査)への切り替えです。
査察は立件(刑事事件化)を目的とした手続きで、状況によって身柄拘束(逮捕)や起訴、有罪へ進む可能性が出てきます。
つまり、通常の調査のまま終わるのか、どこかの時点で“グレードアップ”するのかが重要な分岐点になります。
第2章 通常の税務調査と査察(強制調査)の違い

通常調査と査察の違いを知ることは、正しく怖がるための第一歩です。
通常調査は、事前の連絡や日程調整が入り、帳簿や申告内容を確認して不足や誤りを修正するための行政手続です。
多くの場合、修正申告+追納で完了します。
一方で査察は、刑事責任を問う前提で証拠を収集する強制手続です。
無告知で多数の担当者が一斉に来訪し、任意の協力ではなく強制的な捜索・差押が行われます。
ニュースで映る「ダンボールの山と、人の列」の劇的なシーンは、まさにこのフェーズでの映像であることが多いでしょう。
最初の接触はいきなりの訪問とドア越しの名乗りから始まるのも、通常調査との大きな違いです。
第3章 なぜ“グレードアップ”するのか?

通常調査が査察に切り替わる背景には、社会的注目度・金額・悪質性という三つの軸があります。これらは単独でも、複合でもトリガーになり得ます。
〇社会的注目度
芸能人やインフルエンサー、業界内の著名人など、影響力のある人物は、いわゆる「一罰百戒」の観点から見せしめ的に扱われやすいことがあります。
ニュースで取り上げられる機会が増えるほど、捜査機関側も「社会的意義」を意識する傾向があるのは否めません。
〇金額の多額性
目安として脱税額が1億円を超える規模になってくると、査察への切り替え可能性は一段と高まります。
もっとも、金額だけがすべてではなく、継続性や組織性、隠蔽の巧妙さなども評価対象です。
〇悪質性
不正スキームを広めたり、セミナーや動画で手口を教唆したり、複数人で口裏合わせをしたりするなど、意図性と組織性が強いケースは、査察のターゲットになりやすい傾向があります。
第4章 査察でも必ず逮捕ではない

査察に入ったからといって、必ず逮捕ではありません。逮捕の是非を大きく左右するのは、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれの二点です。
逃亡のおそれは、国外への出国や所在不明化の懸念がある場合が典型です。国籍や滞在実態に関わらず、「連絡がつかない」「帰国の意思が不明瞭」などの状況は、逮捕へ傾きやすい要因です。
証拠隠滅のおそれは、関係者による口裏合わせ、裏契約書や現金の隠匿・廃棄、データの削除・改ざんなどが該当します。
なお、指示した本人だけでなく、指示に従って隠匿や廃棄に関与した周辺者にも、逮捕のリスクが及び得る点には注意が必要です。
第5章 無予告来訪=査察なのか?

「無予告で来た!」この瞬間の判断で明暗が分かれやすくなります。
無予告だからといって必ず査察とは限りません。通常調査でも無予告はあり得るため、まずは令状の有無、担当部署名、来訪目的を丁寧に確認します。
焦りから質問応答記録書に安易にサインすると、後の主張が極めて難しくなります。
税理士が同席できるなら日程再調整を求め、いないなら税務調査に強い税理士にその場で連絡し、税務代理の委任手続きを検討しましょう。
ここで「言いなり」にならず、適法な手続と権利を踏まえた行動に切り替えることが肝心です。
第6章 7年課税を避けるために
調査過程で問われやすいのが、当初申告をどのように行っていたかです。
「売上は何を見て、誰が、いつ集計したのか」「経費の大口科目(仕入、外注費、人件費など)をどの資料で確認し、どう計上したのか」。この業務フローの説明力が弱いと、**重加算税や課税期間の延長(最大7年)**の土俵に乗せられかねません。
逆に言えば、いつ・何を・誰がを一貫性のある形で説明でき、帳簿・内訳書・月次集計と1円単位の整合が取れていれば、過失の主張余地は広がります。「適当にやっていました」は最悪の答えです。
今日からでも、説明できる運用へ作り替えていきましょう。
第7章 狙われやすい対象と、ありがちな落とし穴
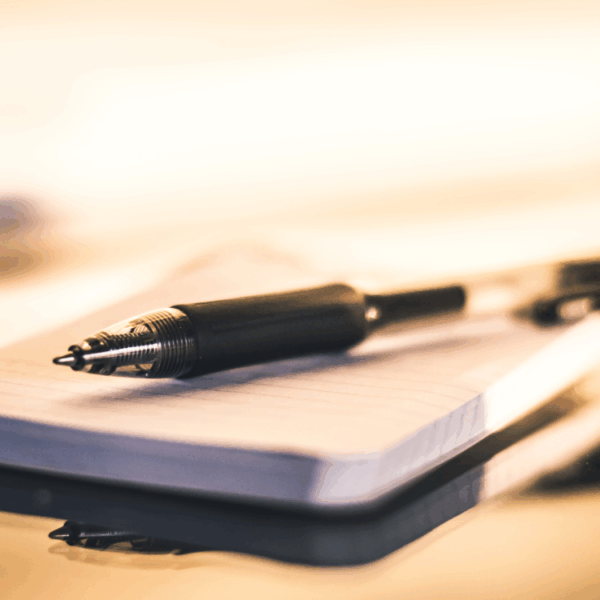
昨今は、芸能人に限らず発信力を持つ実業家やインフルエンサーも注目対象になりがちです。
SNSやYouTubeでの収益、公式LINEや外部決済の活用など、収入口が分散しやすい時代だからこそ、別口座での入金管理や小口の放置が、結果的に申告漏れを招くことがあります。
過激な発信や派手な生活は、それ自体が違法ではありません。
しかし、見られている前提で帳簿と申告の整合性を固め、「説明できるか」を常にチェックしましょう。
日常の小さなズレが、調査の現場では大きな「矛盾」に拡大して見えます。
おわりに

税務調査は“怖いイベント”ではなく、正しい手順で対処すれば乗り切れるプロセスです。
怖さの正体は、仕組みを知らないことと、準備不足にあります。
今日触れた見極め方と初動、そして説明できる申告運用を身につけておけば、たとえ突然の来訪があっても、落ち着いて対処できるはずです。
私たちも、「お客様に大丈夫ですと言える税務調査の専門家」として、皆さまの不安を一つ一つ解きほぐしていきます。
また、公式LINEに登録いただいた方には、調査前後に役立つ実務ツールを無料でお配りしています。
〇無予告来訪チェックリスト(当日の初動対応)
〇質問応答記録書で困らないための要点集
〇査察のサイン早見表(見極めリスト)
👉 公式LINE登録はこちら

👉 YouTubeで解説動画を見る
税務調査についてもっと詳しく知りたい方はこちらの動画をぜひご覧ください。
「完全対応マニュアル(2時間動画)」