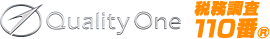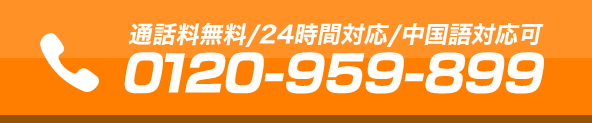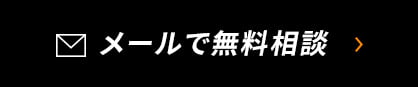目次
はじめに

競馬や競輪、パチンコなどの「ギャンブルで得たお金」にも、当然ながら税金がかかる可能性があります。
特に競馬の払戻金については、「一時所得」となるのか「雑所得」となるのかで課税額が大きく変わるため、正しい知識が不可欠です。
今回は、最高裁で大きな判断が下された平成29年12月15日の判決を中心に、その経緯と注意点をわかりやすく解説します。
現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」
という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

1 平成27年判決と通達改正:経費が認められる可能性があるケース

平成27年3月10日の最高裁判決(以下「平成27年最判」)は、競馬の払戻金が「一時所得」とは限らず、「雑所得」に該当する可能性があると初めて示しました。
この判決では次のような点が重要です。
〇馬券の購入と払戻しの受取りが「一体の経済活動」といえる場合
〇営利を目的とした継続的な行為から生じた所得といえる場合
〇その場合、外れ馬券の購入費も経費として認められる
ただし、この判決は特殊な事例(自動購入ソフトを使って継続的に馬券を購入していたケース)をもとにしたものであり、明確な判断基準が示されたわけではありません。
この判決を踏まえて、平成27年5月29日に所得税基本通達が改正され、「営利を目的とする継続的な行為を除く」という文言が追加されました。
しかし、具体的な例は平成27年最判の事実関係をなぞっただけであり、一般化できる基準にはなりませんでした。
2 平成29年判決:自動購入でなくても雑所得と認定されたケース
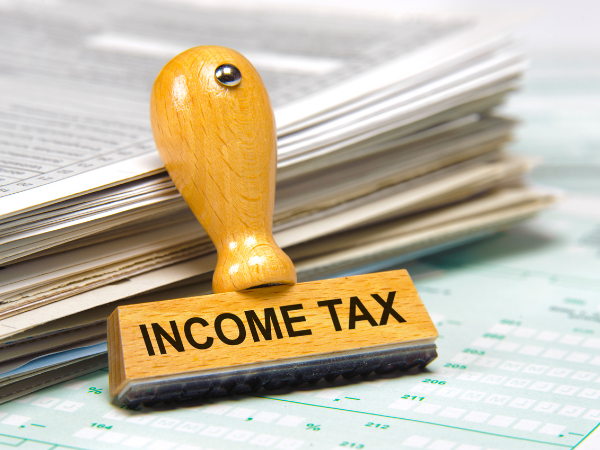
平成27年最判の約2か月後、東京地裁で再び馬券の所得区分をめぐる訴訟がありました。この事案では以下のような特徴がありました。
〇平成17年から平成22年までの6年間で継続的に利益を上げていた
〇馬券購入総額は約72億7千万円、払戻金は約78億4千万円
〇購入方法は自動購入ソフトではなく、独自のノウハウによるもの
東京地裁は「一般的な競馬愛好家と大差ない」として一時所得と判断しましたが、東京高裁は次の理由で逆転し「雑所得」と認定しました。
〇6年間という長期にわたり多額の利益を継続的に得ていた
〇「回収率が100%を超える馬券を選別できるノウハウを持っていた」と推認できる
〇一連の馬券購入は「一体の経済活動」といえる

国側は上告しましたが、最高裁第二小法廷は平成29年12月15日に上告を棄却(平成29年最判)。
雑所得と認定した東京高裁判決が確定しました。
最高裁は次の点を重視しています。
〇行為の期間・回数・頻度・利益の規模などを総合的に考慮すること
〇「年間を通じてほぼ全レースで馬券を購入し、6年間継続して利益を出していた」点を評価
〇「回収率が総体として100%を超えるように購入していた」と認定し、営利目的と判断
その結果、外れ馬券の購入代金についても「払戻金を得るために直接必要な経費」として認められました。
3 判決後の通達改正:自動購入が必須ではない
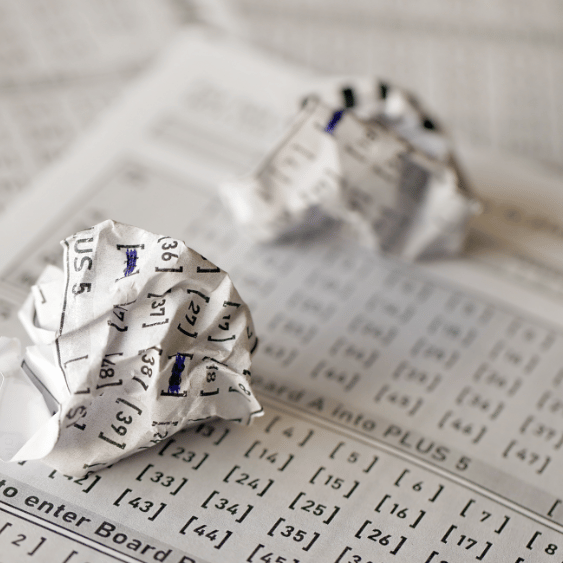
平成29年最判により、「雑所得」と認められる要件が大きく広がりました。ポイントは以下の通りです。
〇自動購入ソフトの使用は必須ではない
〇着順予想など人の判断を伴っていても、一定の選別方法で継続的に購入していれば該当し得る
〇「6年連続で利益が出ていた」という利益の継続性が極めて重要
これを踏まえ、平成30年6月29日に通達が再改正され、平成27年・29年両判決を踏まえた形へと修正されました。
ただし、これは「雑所得と認められる特殊な事例がある」と示したにすぎず、広く一般に適用できるわけではありません。
4 平成29年判決以降の裁判例:雑所得と認められた例はほぼない

平成29年最判後も、馬券やその他のギャンブル所得に関する裁判が地裁以上で約8件出ていますが、そのうち雑所得と認められたのは地裁で1件のみ。
控訴審では一時所得と判断され、確定しています。
つまり、平成29年最判以降、「雑所得」として認められたケースは事実上存在していません。
注意喚起:安易な申告はリスク大
今回の判決を見て「外れ馬券も経費になる」と考えるのは危険です。
平成29年最判は非常に特殊な事情が揃ったケースであり、次のような条件を満たさないと同様の判断はまず得られません。
〇複数年にわたり継続して利益が出ている
〇利益の総額が大きい
〇選別や購入方法に再現性・合理性がある
一時的な的中や趣味の範囲での馬券購入では「一時所得」とされる可能性が極めて高く、外れ馬券の経費算入は認められません。
安易に経費を申告すれば、税務調査で否認され追徴課税を受けるリスクがあります。
おわりに
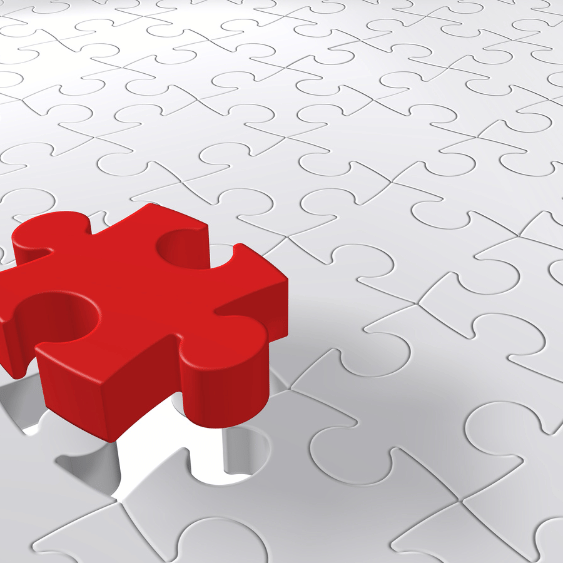
ギャンブル所得の課税は、表面的にはシンプルに見えても、実際には非常に複雑です。
平成29年最判は重要な判断ではありますが、「雑所得」となるのはあくまで例外的なケースです。
税務調査のリスクを避けるためには、判例の内容を正しく理解し、自分のケースが該当するのか慎重に検討することが欠かせません。
少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、正しい申告と備えを行うことが重要です。
他にも詳しい事例や具体的な解説を知りたい方は、私たちのYouTubeチャンネルで「税務調査対応マニュアル 完全版」を公開中です。
ぜひ一度ご覧ください。
さらに、公式LINEにご登録いただくと、5大特典+さらに2つの特典をご用意しております。