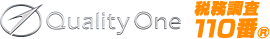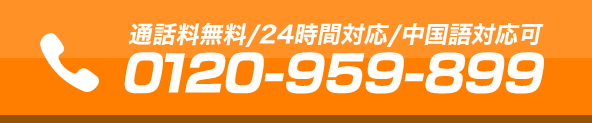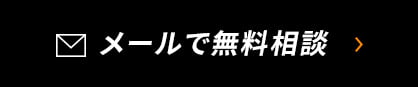はじめに
ここまでの4回で、税務調査の臨場前の対策について説明をしてきました。

今回はいよいよ、調査担当者がご自宅やオフィスに臨場した際の対応について詳しく解説していきます。
税務調査は、税理士任せにしてしまいがちな部分もありますが、臨場日にあなた自身がどう対応するかによって、その後の税務署とのやり取りや、最終的な追徴課税の有無が大きく変わってきます。
この記事を読むことで、調査官の思考や行動の意図を知り、適切に備えることができるようになります。
「知らなかった」では済まされない現場対応のリアルを、ぜひこの機会に押さえておきましょう。
現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」
という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

目次
臨場日の流れとは?

法人であれば調査の初日、個人の場合はその1日が「臨場日」となります。
その当日の流れは以下のようになります。
〇自己紹介(5分)
〇雑談(30分〜1時間)
〇事業概況の聴取(1〜2時間)
〇現況確認調査(30分〜1時間)
〇帳簿書類の確認
〇質疑応答
〇質問応答録の作成
〇帳簿書類の借用(30分程度)
それぞれについて、順を追って見ていきましょう。
【1】自己紹介と身分証の確認

「自己紹介」は、調査官が行うもので、単なる儀礼的なものではなく、法律に基づく身分提示の義務があるため行われます(国税通則法第74条の12)。
提示されるものは最低2枚あります。
身分証明書
担当者の所属、氏名、役職などが記載された写真付きの証明書です。発行者は税務署長または国税局長です。
質問検査証
所得税・法人税・消費税などに関して調査ができる権限を示すものです。
記載のない税目に関しては法的に質問・検査ができないため、質問されても答える義務はありません。
【2】雑談の有無で担当者の力量が見える

雑談がない担当者が最近では主流になっています。
その背景は以下のとおりです。
〇調査手続きの法定化によって「記録」が義務化された
〇業務負担が増え、臨場調査にかけられる時間が減少
〇若手育成プログラムにより調査がマニュアル化
つまり、雑談をする余裕も能力もない担当者が増えています。
一方で、雑談がうまい担当者は「自然に情報を引き出す」スキルを持っており、非常に注意が必要です。
例えば…趣味やプライベートの話から交際費との矛盾を探すや仕事の進め方から帳簿の作成頻度を推測するなど。
天気の話だけで終わる担当者は逆に安心です。
聞かれたことにだけ答え、書類を見せればOKという対応で済みます。
【3】事業概況の聴取がスタート

雑談が終わると、いよいよ本格的な調査が始まります。
主に以下のようなことが聞かれます。
〇現在の事業内容
〇事業開始の時期
〇売上・仕入の決済方法、サイクル
〇請求書・領収書の管理状況
〇資産取得状況やローンの有無
〇帳簿の作成状況や頻度
〇確定申告書の作成者・作成時期・方法
とくに最後の質問は非常に重要です。
「税金を少なくするつもりで申告した」と受け取られると、重加算税の対象となります。
調査官は聞き方を変えながら何度も確認してきますが、「意図的に少なく申告した事実はない」と明確に伝え続けましょう。
【4】現況確認調査:一番見られているところ

このパートでは以下のような確認が行われます。
〇レジ周り(現金残高)
〇通帳・請求書などの保管場所
〇パソコン内のデータ
特にレジ周りの現金残高は、「帳簿と残高が合っていない → 売上除外があるのでは?」という疑いに直結します。
その対策としては、臨場日前の1週間程度、現金残高をきちんと合わせておくことが有効です。
【5】帳簿確認と「質問応答録」の作成

調査官は、これまで聴取した内容と帳簿類が一致しているかを確認します。
時間が足りない場合は帳簿を持ち帰るための「借用書」を作成して書類を持ち出します。
このとき、対応時間を13時までに限定すると、調査官はスケジュールを合わせて臨場を早く終わらせようとします。
(例:「午後から予定がある」と事前に伝える)
【6】質問応答録の取り扱い

この記録は、調査官が集めた情報を証拠化するためのものです。
とくに過少申告の意図があったかどうかが焦点になります。
対応ポイント
〇署名は任意です。「本日は署名を拒否します」と伝えましょう
〇曖昧な部分は、断定表現を避けた記載に訂正させる
〇税務署の勝手な解釈での表現は訂正を求める
〇訂正要求の事実も後で交渉材料になります
質問応答録は、後の交渉や判断の場面でも使われる重要な資料です。
一言一句、納得のいく内容になっているかを確認しましょう。
おわりに

以上が税務調査の臨場日当日の流れになります。
臨場日当日で対応できることというのはかなり限られてくるため、とにかく事前対策を前日までにどれだけやったかが重要になってきます。
「臨場日当日で対応すれば何とかなる」と思っているのであれば、それは今すぐ改めて前回までの事前対策を講じてみてはいかがでしょうか。
こちらの動画にも当日について詳しく説明しております。