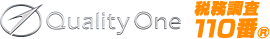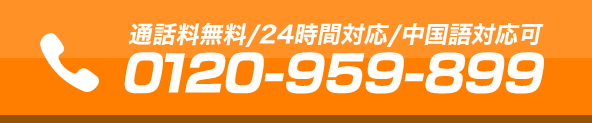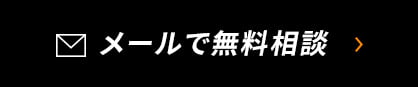目次
はじめに

経営者にとって税務調査は、できるだけ避けたいことのひとつではないでしょうか。
「きちんと申告しているから大丈夫」と思っていても、税務署から突然連絡がきたら不安な気持ちになりますよね。
実際にどんな会社が税務署にマークされやすいのか、逆に「入りたくない」と思わせる会社にはどんな特徴があるのか!?
その答えはどこにあるのでしょうか?
今回は、国税で24年間にわたり調査現場を知り尽くした税理士・星野氏がYouTubeチャンネルで語った内容をもとに、徹底解説します。
現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」
という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

1. 税務署が「入りたくない」と感じる会社とは?
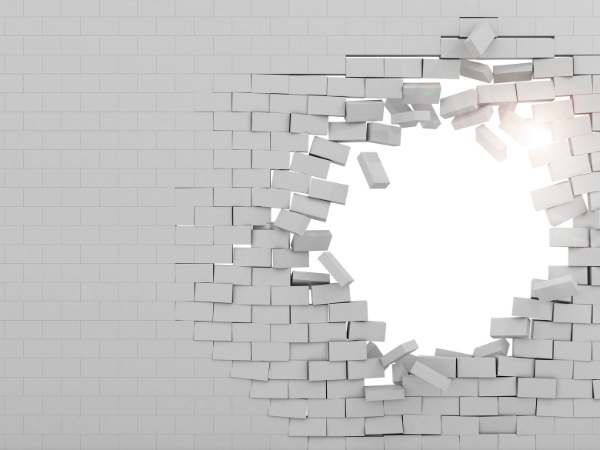
税務署がまず見るポイントは、申告書の見た目です。
計算がきちんと整っていて記載が丁寧、文章もしっかりしているなど。
そのような申告書は税務署にとって「きちんとした会社」という好印象を与えます。
かつて紙で申告していた時代はその見た目から真面目さが伝わりましたが、今は電子申告が主流です。
それでも、文章がしっかりしているか、計算に整合性があるかなど、細かい部分に申告者の態度はにじみ出ます。
このようにきちんと整えられた申告書は、税務調査に入ろうとする側にとっては、ハードルが上がるのです。
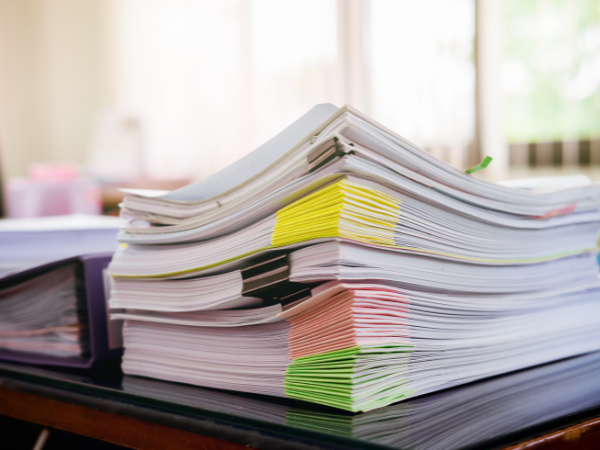
さらに強力な防御策として「書面添付」があります。
これは税理士が申告書に対する見解や計算根拠を明示する制度です。
税務調査を行う前に税理士からヒアリングする手続きがあるため、税務署からすると「一筋縄ではいかないな」という感触になります。
その分、安易に税務調査に入る可能性が下がる確率が高くなります。
国税局も業界ごとに大体の利益率や売上動向を把握しています。
その業界平均から大きく外れていない、売上や利益に大きなブレがない企業は税務署にとって優先度が低い対象となりやすいと言えます。
2. 結果として入りやすい業態とは
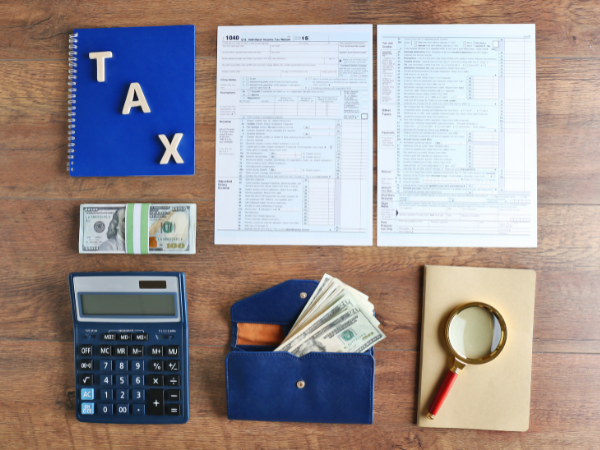
現金取引が主な業態(飲食業や個人サービス業など)は売上や経費が捕捉しにくいため税務調査の対象にされやすい傾向があります。
「気になるから見に行ってみよう」となりやすい業態です。
一方、BtoBで大手取引先があり、入出金の流れが明確な業態(たとえば製造業や建設業)は、税務署から見ても取引が追いやすく、狙われやすい面もあります。
特に業界特有の売上計上のルールや完工基準に沿った計上がされていない場合、調査対象となる可能性が上がります。

また、近年台頭してきた業態やニュースで注目される業界は、税務署にとっても新たな調査対象となりやすいです。
特に税務署がまだ詳しくない業態は、内部で調査ノウハウが蓄積される前に見ておきたいと考えられることもあります。
3. 国税OB税理士に頼めば安心か?

「国税OBだから税務調査に強い」と一概には言えません。その人が国税にいたときにどんな部署にいたのか、どんな業務に詳しかったのかが重要です。
管理職や人事業務が中心だったOB税理士は、現場の細かい法人税や所得税に精通していないこともあります。
表向きの肩書きだけで選ばず、自分の業態に合った専門知識と現場経験があるかをしっかり確認することが大切です。
4. 調査に入りにくくする具体策と注意点
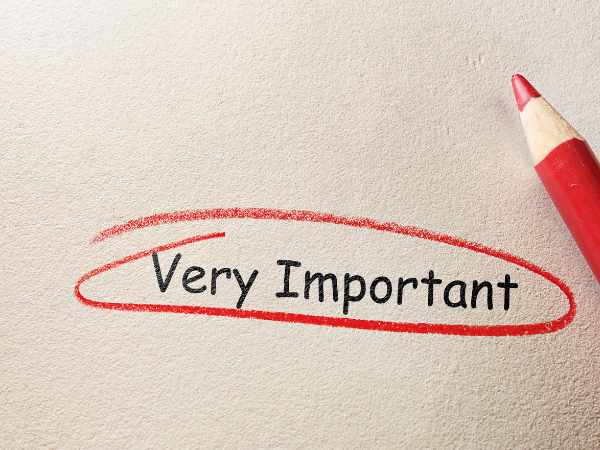
きちんと税理士が監修していることを示す書面添付は、税務調査に入られる可能性を下げる有効な手段です。
融資目的などで利益を無理に増やさないことも重要です。
不自然な利益計上は後から説明を求められるリスクを増やすだけです。
特需や一時的な大きな利益が出た場合には、その背景や理由を申告書の所定欄に記載することで調査官に納得感を与え、調査に入る可能性を低くすることができます。
5. 終わりに

税務調査は、どんな企業にも入る可能性があるものですが、きちんと対策をすることでそのリスクは確実に減らすことができます。
「自社には関係ない」と過信するのではなく、日頃から申告書や帳簿が整っているか、説明できる準備が整っているかを今一度見直してみましょう。
さらに、一度も税務調査が入ったことがないからといって油断は禁物です。
「税務署が入りやすい会社」の特徴に当てはまっていないか、改めて見直すことも大切です。
もし税務調査や対策に不安がある方は、今回の動画でも触れていた通り、税務調査専門の税理士に相談することがおすすめです。
きちんとした対策をして、平穏な経営ができるよう心がけましょう。
こちらの内容について、こちらの動画で詳しく説明しております。