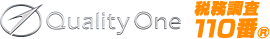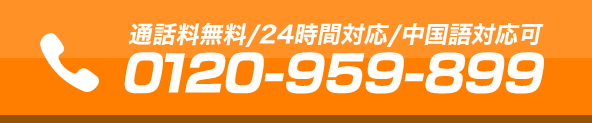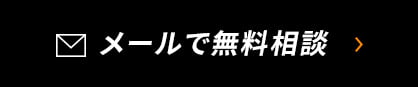目次
はじめに

「外貨を円に換えただけでも課税されるの?」「為替差益ってどう扱えばいいの?」と疑問に感じたことはありませんか?
このブログでは、会社員や副業を行っている方が見落としがちな「申告すべき為替差益」の基本知識を解説します。
特にサラリーマンでも対象になります。
今回は対象となるケースや、課税される経済的利益の範囲、為替差益に関する代表的な6つのパターンを分かりやすく紹介していきます。
確定申告や税務調査で損をしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。
現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」
という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

1 申告が必要な人

日本に住むサラリーマンで、確定申告書の提出義務がある者については、いろいろなケースがあるのですが、代表的なケースとしては次のような者になります。
1.給与の収入金額が2,000万円を超える人
2,給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
3.同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受ける人
一般的なサラリーマンは、副業の利益が20万円を超えると、上記②のケースに該当し、申告が必要になります。
2 経済的利益への課税
商品を販売したり、役務を提供して対価を受け取っていれば、所得金額を認識することはそれほど難しくないと思われます。
しかし、所得税法が課税の対象とする所得は、包括的所得概念という考え方により、原則としてその範囲には制限がありません。
したがって、経済的利益という所得に対しても課税することとしており(所法36①)、経済的利益についての知識が不足していると、申告しなければならない所得について申告漏れとなってしまいます。
たとえば、ふるさと納税の返礼品も、経済的利益に相当します。
経済的利益とは?課税されるタイミングに注意
「経済的利益」と聞くと、たとえば持っている資産の値上がり(評価益)も含まれるなど、非常に広い意味を持つ言葉です。
しかし、所得税法では、評価益があるからといってすぐに課税されるわけではありません。
その資産を売るなどして、実際に利益を得たタイミングで課税されるのが基本的な考え方です。
つまり、まだ売っていない=利益が確定していない段階では、課税の対象にはならないということです。
会社員にとっての「経済的利益」とは?
一方、会社員(使用人)の場合には、会社(使用者)から受け取るさまざまな「経済的利益」が、給与として課税対象になることがあります。
たとえば次のようなケースが該当します。
会社が費用を負担する会食や社員旅行などのレクリエーション
→ 原則として「経済的利益を受けた」として、給与課税の対象に。
ただし、これらには課税しなくてもよいとされる一定の条件があります。
たとえば、レクリエーションの内容が「全社員を対象とした福利厚生の一環」である場合などです(所得税基本通達36-30)。
また、他にも「課税しなくても差し支えない」とされるルールがいくつか定められています(同36-21~29、31~35の2 など)。
3 為替差益

外貨を保有していた場合、為替の変動に応じて評価益や評価損が発生します。このような経済的利益は、外貨を保有しているだけでは課税しません。
しかし、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引を行った場合には、その取引時の円換算額で各種所得の金額を計算するとされます。(所法57の3①)
下記の事例のように、外貨を使用するなどしたときには、円転していない場合でも原則として評価益が実現したものとして課税されますので注意が必要です。
(1)外貨預金の払出し
ドルを預金し、その数年後、そのドル預金を払い出して円に換金した場合
⇒ 預金時と換金時の、ドルと円の為替レートの差額(円換算での為替差益。以下同じ。)は雑所得です。
(2)外貨預金から外貨預金への預け替え
ドルを定期預金にし、その満期時に払い出し、同日に他の銀行に預け替えた場合
⇒ 同一の外貨を保有し続けていることと同様なため、課税関係は生じません。
(3)外貨預金を払い出して、その外貨で不動産を購入

ドルを預金し、その数年後、そのドル預金を払い出して不動産を購入した場合
⇒ 預金時と不動産購入時の、ドルと円の為替レートの差額は雑所得となります。
(4)外貨預金を払い出して、その外貨で金融資産を購入
ドルを預金し、その数年後、そのドル預金を払い出して外貨建MMF(米ドル建公社債投資信託)を購入した場合
⇒ 預金時とMMF購入時の、ドルと円の為替レートの差額は雑所得です。
(5)外貨預金を払い出して、その外貨を異なる通貨(円以外)に換金
ドルを預金し、その数年後、そのドル預金を払い出してユーロ建てで預金した場合
⇒ ドル預金時とユーロ預金時の、ドルと円の為替レートの差額は雑所得です。

(6)ドル建で購入した海外不動産をドル建で譲渡し、その売却代金をドルで預金
海外不動産をドル預金とドル建の借入金により購入し、数年後にドル建てで売却し、その売却代金の一部を借入金の返済に充て、残りを預金した場合
⇒ 不動産取得価額、譲渡費用及び譲渡価額は、それぞれの時のドルと円の為替レートで円換算して算定する。取得資金が借入金か否かは考慮しない。
譲渡所得の金額は、円換算による譲渡価額から譲渡費用及び取得価額を差し引いて計算します。
したがって、為替差益は譲渡所得の金額の中に含まれる(H22.6.28裁決事例集№79参照。なお、外国株式等の譲渡などでも同様です。)。
おわりに|

近年、副業や資産運用、外貨取引を行う方が増えたことで、為替差益に関する課税の見落としも増加しています。
「外貨を円に換えただけ」「不動産を売却しただけ」と思っていた取引が、実はしっかり申告が必要なケースであることも。
本記事で紹介した内容を参考に、取引の種類ごとに課税関係を正しく判断できる目を持つことが、将来的な税務リスク回避につながります。
不安な方は、税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
知らなかったでは済まされない、申告漏れを防ぐ第一歩として、この記事がお役に立てれば幸いです。
もっと税務調査に対して知りたい方はこちらの動画もおすすめです。