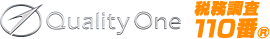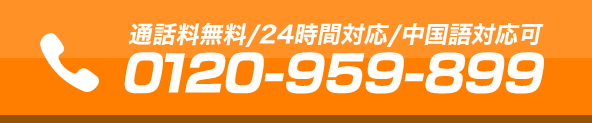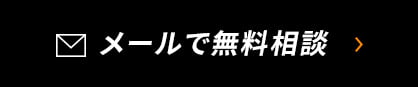目次
はじめに

「寺院や神社は非課税だから税務調査は関係ない」と思っていませんか?
たしかに宗教活動に関わる収入は原則非課税です。
しかし、それは税務調査の対象外であることを意味しません。実際に税務調査が行われ、申告漏れを指摘された事例も存在します。
本記事では、寺院・神社・宗教法人に対する税務調査の実態やチェックされやすいポイント、過去の事例、そして調査時の注意事項まで詳しく解説します。
正しい知識を備え、万全な対策を講じるための一助となれば幸いです。
現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」
という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

第1章 宗教法人は税務調査の対象になるのか?

「宗教法人=非課税」というイメージから、税務調査は無縁だと思われがちですが、実際には調査対象です。
宗教活動そのものは非課税ですが、給与や収益事業に関しては課税対象となります。
したがって、税務署はこれらの側面に着目し、調査を行います。
第2章 税務調査の件数と傾向

国税庁の「平成27事務年度における公益法人等の調査事績」によると、宗教法人を含む公益法人への税務調査件数は以下の通りです。
〇平成26年:868件
〇平成30年:429件(約半減)
調査対象となる公益法人数は約35,109件であり、調査件数はわずか約1.2%。確率としては約80年に1度とも言われますが、「自分のところには来ない」と油断するのは危険です。
第3章 税務調査で見られる主なポイント

税務調査では、宗教法人の源泉所得税の処理と収益事業の申告状況が重点的にチェックされます。
① 源泉所得税の適正な処理
〇住職や宮司、職員への給与や退職金は課税対象。
〇税理士や外部専門家への報酬も源泉徴収が必要。
注意すべきケース
〇飲食代や生活費の負担 → 給与扱い(源泉徴収必要)
〇弟子の学費負担 → 給与扱い(同上)
② 収益事業の申告漏れ
課税対象となる収益事業は非常に線引きが難しく、特に物販に注意が必要です。
非課税扱いになる物販(喜捨金扱い)
〇お守り
〇お札
〇おみくじ
課税対象となる物販(収益事業扱い)

〇絵葉書
〇御朱印帳
〇キーホルダーなど
第4章 税務調査で「過去帳」の開示は必要か?

税務調査では、宗教法人の非課税収入(布施・奉納金・会費・献金・賽銭・寄附金など)が適正に計上されているかが重点的に確認されます。
その中で調査官が過去帳の提出を求めてくるケースがあります。
なぜ過去帳が求められるのか?
調査官は、例えば「故人の逝去日」や「葬儀日」などから、実際に布施や奉納金などの非課税収入が正しく記録されているかを検証しようとします。
帳簿の内容と実際の宗教活動が一致しているか確認するため、過去帳の内容が「裏付け資料」と見なされるのです。
法的義務はないが慎重な対応が必要
過去帳の提出には明確な法的義務はありません。
しかし、調査現場では「雰囲気に押されて提出してしまう」ケースも多く見られます。
一方で、明確に拒否すると「何かやましいことがあるのでは」と疑われるリスクもあります。
過去帳の性質とリスク
過去帳には、以下のような個人情報が含まれています。
〇 故人の氏名、没年月日
〇 施主(遺族)の氏名
〇 葬儀日、法要日 など
これらは信徒との深い信頼関係に基づく記録であり、安易な取り扱いは寺社の信頼を大きく損なう可能性があります。
推奨される対応方法
過去帳の開示を求められた際には、以下の対応をおすすめします。
〇 その場で即答しない
〇 「一度、顧問税理士に確認します」と伝える
〇 税務調査に強い税理士に相談し、提出の必要性・範囲を判断
〇 必要であれば、提出内容を限定し、一部黒塗りや匿名化を行う
税理士を通じて、調査官と「開示範囲の交渉」を行うことも可能です。過去帳は宗教法人の信頼資産でもあるため、取り扱いには細心の注意が求められます。
おわりに

宗教法人は「非課税だから安心」と思われがちですが、税務調査の対象外ではありません。特に源泉所得税の処理や収益事業の申告においては、誤解やミスが調査対象となりやすく注意が必要です。
また、「過去帳」など宗教的・個人的な記録の取り扱いも慎重な対応が求められます。税務調査が行われた際には、税務調査に強い税理士に相談し、信頼と透明性を確保した対応を心がけましょう。
正しい知識と備えが、宗教法人としての信用を守る鍵となります。
こちらの動画にも宗教法人に関する内容を詳しく説明しております。
併せてご視聴ください。