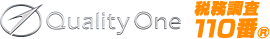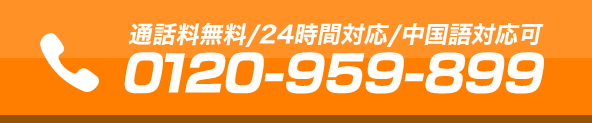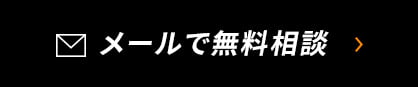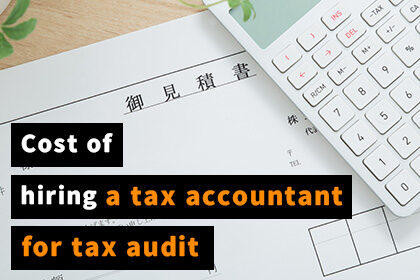目次
はじめに

「確定申告をし忘れた…」「期限を過ぎてしまったけれど、今からでも間に合う?」
こうした不安を感じたことはありませんか?
本記事では確定申告を期限までに行わなかった場合にどうなるのか、その際に課される「無申告加算税」の仕組みや金額、状況別の対応策などを、制度の変更点も含めて詳しく解説しています。
この記事を読むことで、万が一期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけペナルティを軽くする方法や注意点がわかり、
適切な対応が取れるようになります。
これから確定申告をする方や、過去にうっかり申告が遅れてしまった方にも、役立つ内容です。
1 期限後申告についての加算税

確定申告書の提出義務があったにもかかわらず、その申告期限までに提出できなかったときはどうしたらよいのでしょうか。
また、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
確定申告書の提出義務がある者とは、事業者であれば、細かいことは省いて簡単にいえば、納税額がある人です。
確定申告は、その法定期限である3月15日までに申告をし、納税もその申告期限までにしなければなりません。
1日でも期限に遅れて提出された申告書は、期限後申告書といい、その提出後、その納税額に対して一定の割合で無申告加算税を賦課するという通知書が税務署から送られてきます。
期限後申告を行う場合
①税務署からの調査の事前通知がある前に申告した場合
②調査の事前通知後、調査による決定を予知する前に申告した場合
③調査開始後(決定の予知後)に申告した場合
それぞれの場合により、無申告加算税の賦課割合が違ってきます。
(1)調査の事前通知前に提出した場合

税務署からの調査の事前通知がある前に自主的に申告した場合(※決定の予知前に限る。)でも、納付すべき税金(1万円未満切捨て。)の5%の無申告加算税が賦課決定されます。
ただし、次のいずれかの場合は加算税は不適用となります。
①災害が起きた場合や交通、通信の途絶などで、誰もが確定申告を行うことが困難だった場合
②納付は法定申告期限内に済んでおり、かつ申告書の提出は法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
これに加えて、期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年以内に無申告加算税又は重加算税を賦課されたことがなく、かつ当該無申告加算税が不適用となる措置(①を除く。)を受けていないこと。
※【決定の予知前とは】
納税者に申告義務があるという情報を税務署が把握していると納税者が知ったとき、いずれ決定処分があると予知できたことになります。
したがって、一般的には調査の通知や、所得内容についてのお尋ね文書が来る前の場合は予知前といえますが、取引先に調査が入り、そこから無申告であることがばれてしまったというような場合、その調査が自分に波及すると知った後は、決定の予知前には該当しないと考えられます。
(2)事前通知後、調査による決定を予知する前に申告した場合
調査の事前通知があっても、調査がまだ開始されておらず、調査により決定がされることを予知する前に自主的に期限後申告書を提出した場合、無申告加算税の割合は納付すべき税金の10%(50万円超300万円以下の部分は15%、300万円超の部分は25%(300万円超については令和5年分以降の申告に適用。))となります。
(3)税務署の指摘があってから、又は調査開始後(決定の予知後。)に申告した場合

無申告加算税の割合は、納付すべき税金の15%(50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%(300万円超については令和5年分以降の申告について適用。))となります。
(4)繰り返し行われる無申告への対応

これまで、申告加算税の期限後申告をした日の前日から起算して5年前の日までの間に、無申告加算税(決定の予知後のもの。)又は無申告重加算税が課されたことがあるときは、その期限後申告に基づき納付すべき税金の10%の金額が加算されるとされていました(加重措置①)。
令和5年分以降の申告については、重大な違反である無申告を防止する観点から、上記のとおり、納付すべき税額が300万円超の部分についても区分し、50万円超300万円以下の部分に係る割合に、10%の金額が加算されることとされました。
このほか、繰り返し行われる悪質な無申告を未然に防止するため、更なる実効的な措置の整備がされています。
令和5年分以降の申告については、前年度及び前前年度の国税について無申告加算税が課される者(調査通知前、かつ予知前に課されたものを除く)が更なる無申告行為を行う場合(調査通知前、かつ予知前に課されたものを除く)には、納付すべき税金の10%を加算するとされています(本措置と加重措置①の両方の要件に該当した場合、いずれかが適用される)。
そのほか、無申告に対するペナルティではありません。
しかし、令和5年分以降の申告については、税務署の調査において、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の提示等をしなかった場合及び帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税金の10%の金額が無申告加算税に加算されます。
また、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合は、納付すべき税金の5%の金額が無申告加算税に加算されます。なお、この措置は、過少申告加算税についても同様です。
2 期限内に申告できない場合
無申告行為は、申告納税制度の根幹を揺るがす重大な違反であると考えられることから、令和5年の税制改正により、無申告の繰り返しの度合いや税額に連動して、無申告加算税が非常に高割合になりました。
また、記帳がない場合や不備がある場合には更にペナルティが課されることとなっています。(期限内申告でも同様)
申告期限にどうしても間に合いそうもない場合、一旦概算で少し少なめに申告して、後日修正申告を行うという方法もあります。
申告ができなかった場合は、税務署からお尋ねや調査の事前通知がある前に、早急に、申告をすることが大切です。
また、確定申告がスムーズに期限内に行えるように、年が明けたら決算が行えるよう日頃から記帳を正しく行うことが一番重要です。
まとめの文

確定申告をしない、あるいは期限に遅れてしまうと、無申告加算税というペナルティが課されるだけでなく、その後の税務対応にも大きく影響します。
特に繰り返しの無申告や帳簿の不備がある場合には、加算税の割合が大きくなり、負担も重くなります。
重要なのは、「期限を守る」「日頃から帳簿を整備しておく」という基本の積み重ねです。
もし期限内の申告が難しい場合は、できるだけ早く自主的に申告することで、ペナルティを軽くする余地も残されています。
併せてこちらの動画をご覧ください。