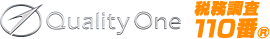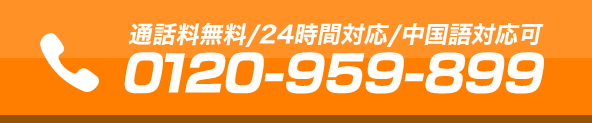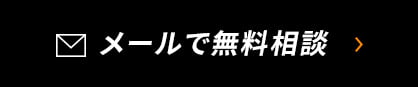前回の記事では、税務調査の全体像や基本的な流れについてご紹介しました。
今回はもう少し深掘りして「税務調査にまつわる数字」をテーマにお話していきます。
調査件数や調査対象の選び方、もし調査に入られた場合にかかる金銭的負担まで、
実際に寄せられるご相談や現場の感覚も交えて解説していきます。
「税務調査ってそもそも自分には関係ないよね?」と思っている方にも、一度は読んでいただきたい内容となっています。
この記事を最後まで読むと「自分が調査対象になりうるのか」「もし来たらどれくらい払うことになるのか」が明確になります。
現在、税務調査に関して質問や不安なことがある方は、24時間対応「税務調査110番」までお問合せください。

目次
税務調査の件数とその内訳

国税庁は毎年11月に、その年の調査実績を公表しています。
公表時期が11月というのは、国税庁の業務年度が7月〜翌年6月となっているためです。
前年の7月から6月までに行った調査の結果をとりまとめて発表しています。
以下が、最近5年間の調査件数の一覧です。
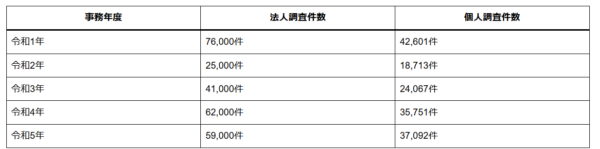
税務調査に「当たる」確率はどのくらい
令和2年度だけはガクンと件数が落ちています。これはコロナ禍によって調査業務が大幅に自粛されたためです。
その後は段階的に回復し、現在ではコロナ前の水準まで戻ってきています。

調査件数だけではピンとこないかもしれませんので、確率で見てみましょう。
総務省の統計(2016年の経済センサス)によれば、法人は約188万社、個人事業主は約198万件存在しています。
この数字をもとにすると、以下のようになります。
- 法人が調査を受ける確率:およそ4%(=25年に1回)
- 個人事業主:およそ2%(=50年に1回)
ここで「え、意外と少ないじゃん」と思われる方もいるかもしれません。
ですが、実際には「もっと頻繁に税務調査を受けている会社」を見たことがあるという方もいるはず。
その理由をこれから解説していきます。
調査が来るのはどんなケース?
この「25年に1回」「50年に1回」という確率は、あくまで全体母数に対するものです。実際に税務調査の候補に選ばれるのは、その中のさらにごく一部。
ここで出てくるのが「調査選定」というプロセスです。
税務署や国税局は、すべての納税者を対象にしているわけではなく、あらかじめ「調査する価値がありそうな事業者」を絞り込んでいます。
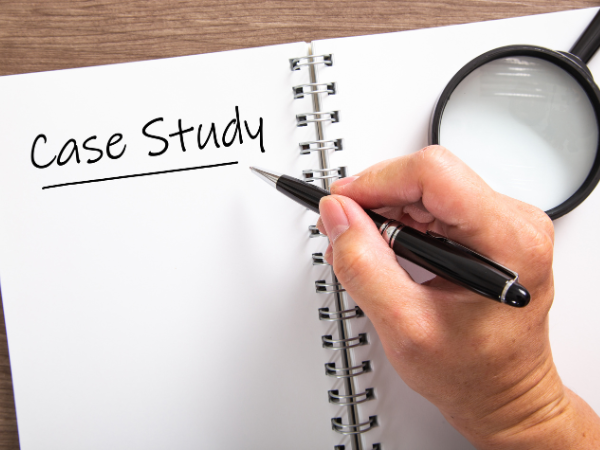
第1段階:調査対象からの除外
まず約半分の事業者が自動的に対象外になります。ここには、いわゆる「優良法人」や、毎年適正な申告を続けている個人事業主が含まれます。
つまり、日頃からキチンと記帳・申告していれば、この段階でスルーされる可能性が高くなります。
もちろん、「ちゃんと納税=お金がかかる」わけなので、これは一種の“保険料”とも言えるでしょう。
第2段階:KSKシステムによる機械判定

次に登場するのが、国税庁の誇る「KSK(国税総合管理)システム」。
提出された申告書の内容を機械的に分析して、異常値がないかをチェックします。
異常値には2つのパターンがあります:
- 業種内での比較:他の同業者と比べて売上や経費が極端に多い・少ない
- 過去の自社比較:前年・前々年に比べて数字が不自然に変動している
この段階で異常と判定されるのは全体の約20%。つまりここでまた絞り込まれます。
第3段階:資料情報との突合
KSKをパスしても油断はできません。税務署は独自に集めた資料情報をもとに再チェックを行います。
例えば以下のものがあげられます
- 銀行からの取引情報
- 不動産の売買履歴
- 他人の調査から出てきた情報(いわゆる「芋づる式」)
ここで対象となるのは、また全体の約20%。
これらの情報を照らし合わせて、「あれ?この申告内容と辻褄が合わないな」と思われたら調査対象になる可能性が高まります。
最終的に調査されるのは約15%
上記すべてを経て、選ばれた事業者はA・B・Cランクに分類されます。
- Aランク(1%未満)→即調査
- Bランク(1%前後)→ほぼ調査
- Cランク(13%程度)→状況次第で調査
この中でA・Bに入ると、ほぼ間違いなく調査の連絡が来ると考えていいでしょう。
調査で払う金額はどのくらい?

ここからは「もし調査が来て、指摘されたら、いくらくらい払うの?」という疑問に答えていきます。
シンプルな事例として、法人・個人どちらにも当てはまる条件で試算してみます。
ケース1:通常の調査(3年間分)
【前提条件】
- 3年間で申告漏れの売上:600万円
- 経費も100万円ほど過少計上
- 税率20%で計算
- 追徴税額はすぐ納付
この金額には加算税(10%)と延滞税(3%)が含まれています。
→ 結果:法人で約825万円、個人で約885万円の納付
ケース2:調査が5年分になったら?
当然、支払いも増えます。単純に1.7倍程度の支出になります。
- 法人:1,375万円
- 個人:1,475万円
ここに税理士報酬(100〜150万円)も追加されるケースが多いです。
ケース3:重加算税(7年間分)
「脱税まではいかないけれど、かなり悪質」と判定されると重加算税が課され、税率が大きく跳ね上がります。
- 法人:1,925万円(うちペナルティ1,113万円)
- 個人:2,065万円(うちペナルティ1,039万円)
延滞税だけで数百万円、つまり利息だけで大変な金額になるのです。
最後に:リスクは突然やってくる

「税務調査なんて、自分には無縁」と思っていても、ある日突然やってくるのが税務調査。
そして、もし調査対象になってしまった場合、最善の対応は「重加算税を避ける」こと。
そのためにも、以下のことに注意していく必要があります。
- 普段から適正な申告を心がける
- 記帳や領収書の管理をしっかりする
- もし心当たりがあるなら、自主的に修正申告する
こうした備えが非常に重要になってきます。
まとめ
税務調査という言葉に、漠然とした不安や恐怖を感じる方も多いと思います。
実際、「何を見られるのか」「いくら払うことになるのか」といった情報は、なかなか表に出にくいものです。
しかし、今回ご紹介したように、調査がどういうプロセスで行われるのか、どれくらいの確率で来るのか、そして万一来た場合にどれほどの金銭的インパクトがあるのかを“知っている”だけでも、心の準備は大きく違ってきます。
税務調査は、正しい知識と事前の備えがあれば、過度に怖がる必要はありません。
むしろ、「きちんとやっていれば何も怖くない」というのが本当のところです。
そんな風に思った方は、今がまさに行動するタイミングです。
税務調査に関して質問がありましたら、弊法人までご連絡ください。
さらにこちらの動画もおすすめです。