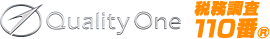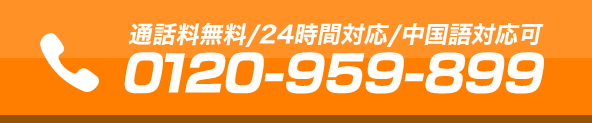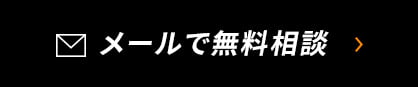目次
はじめに

前回までは、税務調査の連絡を受けたときまでの対応について説明をしてきました。今回は、連絡が来たあとから実際に臨場がある日までに何をすべきか?について解説していきます。
税務調査の連絡が入った後、実際の調査日(臨場日)までの間に、どんな準備をするかでその後の調査の進み方や税務署とのやり取りの難易度が大きく変わります。
この記事では、税務署から調査の連絡があってから、調査担当官が実際にやってくる日までに具体的に何を、どう準備すべきかを徹底的に解説していきます。
現在すでに税務署から連絡があり、「どう対応すればいいかわからない」「申告漏れを指摘されそうで不安だ」
という方は、一人で抱え込まず、すぐにご相談ください。

臨場日までの1ケ月、ここでの準備ですべてが決まる?

臨場日までに何をすればいいかよくわからないこともあり、担当官からは申告の基になった帳簿や請求書などを用意してとしか言われていないから、それを用意すればいいのでは?と思うかもしれません。
しかし、実際に担当官が臨場してみると、事前に用意した帳簿などを見るのは午後からというのがほとんど!
その日は帳簿などを見ずに税務署に持ち帰って見るということもあります。
となると、何を準備すればいいのか迷ってしますよね。
税務調査に向けて準備するものまたはことは、次のようなものになります。
- 税務署から用意するように言われた帳簿や請求書など
- 過去の申告内容の見直し
- 事務所、自宅の整理整頓
- 不要物の処分
税務署から指示された帳簿・書類を整える
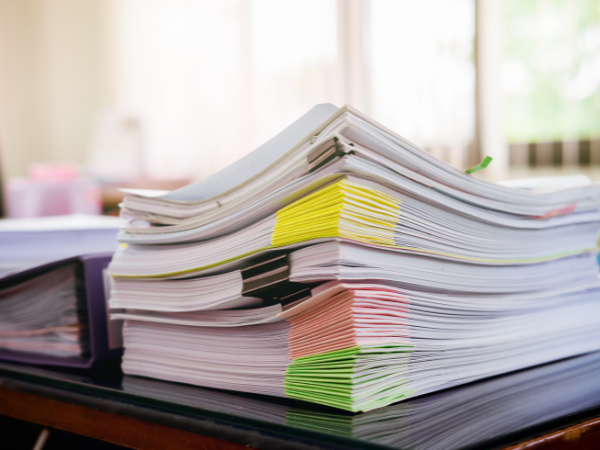
まず、税務署から事前通知を受けたときに言われた「申告の基となった帳簿書類」については、必ず用意しなければいけません。
具体的には以下のとおりです。
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 売上関連書類(見積書、納品書、請求書、領収書、契約書)
- 仕入関連書類(請求書、領収書、在庫管理表)
- 経費関連書類(領収書、出面帳、ETCカード明細)
- 給与関係書類(賃金台帳、源泉徴収簿)
- 預金通帳
- 借入金契約書、覚書
- 株主総会・取締役会の議事録
これらの書類については、パソコンなどでのデータしか保存していない書類は印刷しておきましょう。
また、不足している書類などがある場合は、取引先などに再発行をしてもらうなどして揃えておきましょう。
これは、臨場時の現況調査や反面調査の範囲が無用に広がることを防ぐことができるため、ぜひ準備するようにしてください。
また、これらの書類の準備の仕方ですが、上記の書類ごとにまとめたうえで、「直近期(年)→古い期(年)」と並べることをお勧めします。
担当官は帳簿などを確認するときに直近期(年)から見ていくためで、帳簿などを見ている時間を短縮することができます。
過去の申告内容を見直し、自主修正の判断を

帳簿などの準備ができたところで、過去の申告内容の見直しをして、自主修正をしましょう。
ここでの見直しとは、見つかったミスや不正計算を隠すことをするためではないので、こちらは間違えないようにしてください。
ここでの目的は、以下のものになります。
- 調査臨場日までに自主修正をすることにより
- 過去のミスや不正計算を解消して、加算税を少なくすること
- 重加算税をかけられる可能性をなくすこと
もしミスなどが見つかり、それを隠そうとして書類の改ざんなどを考えていたら、絶対にやってはいけません。
なぜなら、これをやっても他の書類などで必ず担当官に見つかってしまいますし、書類の改ざんなどが見つかってしまうと、重加算税をかけられることがほぼ確定となってしまいます。
異常値のチェックとその原因の特定

もしミスなどを見つけたときは、臨場日までに自主修正をすることをお勧めします。
とはいえ、どのようにミスを見つけていくかわからないかと思うので、具体的にどのように見つけていくかについて説明していきます。
まず最初にすることは、「決算内容に異常値がないか」の確認です。
この決算内容の異常値というのは、同じ科目(売上、外注費など)の金額が他の年と比べて50%以上増減しているようなもののことをいいます。
異常値を見つける方法は、直近5期(年)分の決算書(収支内訳書)を横に並べて見ることです。
そうすると、特定の科目の異常値がよく見えてきますので、その異常値となっている原因を解明していきましょう。
私的な費用のつけ込み、単純な入力誤りなどがあると思いますが、その原因が正当なものであれば「遠くへの出張費用など」、臨場日当日にそれを説明できる準備をすれば大丈夫です。
そうでない原因(単純なミスや不正計算など)の場合は、すぐに自主修正に向けた準備をして、臨場日までに提出を終わらせましょう。
そうすることで、加算税の費用的な負担も減らせ、さらに対応時間や調査期間も短くできるというメリットがあります。
この作業は、実は担当官も臨場前に同じように行っていて、この異常値の科目を中心に質問・検査をしてくる予定だからです。
事務所や自宅の整理整頓で見られる範囲を限定

申告内容の見直しが終わったら、次にすることは、事務所や自宅をキレイにすることです。
ここでの目的は、「担当官に気持ち良く調査をしてもらう」ことではなく、
臨場日に必要な書類を臨場場所にまとめるということになります。
これには2つの目的があります。
- 調査をスムーズに進める
- 余計な場所を見られないようにする
必要な書類を面接する机などにまとめて置いておくことで、保管場所まで取りに行く手間を省けますし、事務所や自宅の様々な部屋で現況確認調査されることを防げます。
整理のポイントは以下のとおりです。
- 必要な書類は面接テーブルにすべて出す
- 書類の保管場所は1か所にする
- その保管場所は面接テーブルのそばに置く
- 今回の調査に関係ない書類は別の部屋に保管
これができていれば、書類がある部屋の中だけで調査が完結できます。
不要な物の処分で「余計な疑念」を回避
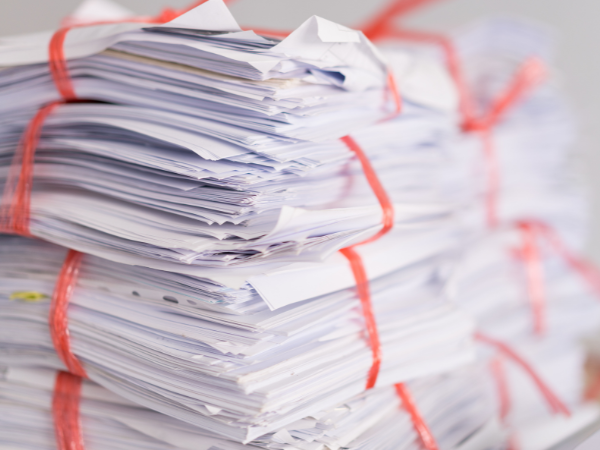
最後に不要な物の処分です。ここでいう「不要な物」とは、以下のようなものです。
- 8期(年)以上前の書類
- 集計などで作成したメモ書き、集計表(データ)
- 直近7期(年)に取引のない取引先の名前が入ったカレンダーなど
- 業務に関係のない個人的な趣味・嗜好に関係したグッズ
これらは「担当官に余計な疑念を抱かせない」ために処分することが重要です。
特にメモ書きや集計表は、法律上の帳簿ではありませんが、税務署の担当者はこれを探しています。
なぜかというと、過少申告の「意図」を立証する証拠になりうるからです。
たとえば、売上の請求書が1枚申告されていなかった場合、単体では意図的かどうかわかりません。
しかし、その請求書も含めた集計メモが残っていて、マーカーやチェックがされていたらどうでしょうか?
それがあることで、「意図的に申告していなかった」と担当者は判断し、重加算税を課す流れになります。
こうした最悪のシナリオを防ぐためにも、不要なメモや資料は保管せず、もし必要なら調査場所とは別の場所に保管するようにしてください。
おわりに
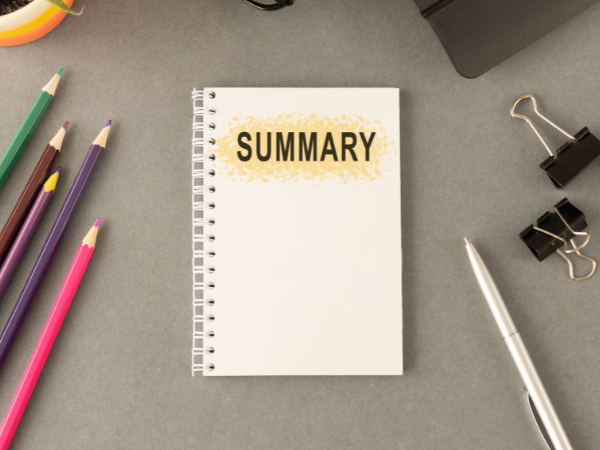
臨場日までにやるべきことは、思っている以上に多岐にわたります。
事前準備をどれだけ完璧にしたとしても、当日に何かしらの「もっとやっておけば…」は生じます。
ですが、それが“後悔”だけで済むか、“高額な追加納税”につながるかは、今この準備にかかっています。
「どう準備したらいいかわからない」「どこまでやれば安心か知りたい」そんな方は、ぜひ私たちにご相談ください。
さらにこちらの動画でも詳しく、解説しておりますので、併せてご視聴ください。